理解の構造と共通基盤の話
本日はちょっと難解なことを書きます。理解の構造についてのお話です。 さて、同じニュース、同じ映画、同じ本に触れても、そこから得られる情報量というのは、その人物の世の中を捉える枠組みの成熟度によって千差万別です。 奥深い枠…
算命学をはじめとする東洋思想の学び舎です
 勉強法
勉強法
本日はちょっと難解なことを書きます。理解の構造についてのお話です。 さて、同じニュース、同じ映画、同じ本に触れても、そこから得られる情報量というのは、その人物の世の中を捉える枠組みの成熟度によって千差万別です。 奥深い枠…
 勉強法
勉強法
同じことを繰り返し質問される、というのは、けっこう大きな挫折感のようなものがあるのですが、 一方で、自分の理解と説明力が問われているようにも感じられるもので、改めて理解を掘り下げ直す良いきっかけにもなります。 本日、no…
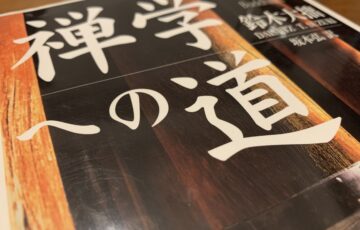 勉強法
勉強法
夏休みの課題図書、というのがいまだにあるのかどうか知りませんが、 私が子供の頃に、大人にプレゼントしてもらった本として、覚えているのは以下の3冊。 『アルジャーノンに花束を』『モモ』『トムは真夜中の庭で』 いずれも、名作…
 勉強法
勉強法
算命学に限らず、いわゆる、占術といわれるものは基本的に、この宇宙が相似で出来ていることを前提としています。 これを端的に表しているのは、「天にあるものは地にある」…という言葉ですが、 他にも、ミクロコスモスとマクロコスモ…
 勉強法
勉強法
このところ、大学の入学式をYouTubeでせっせと観ています。理由は、「新しく何かをスタートする気」というのを感じたいから。 年齢を重ねると、ついつい初心を忘れがちですけれど、入学式において各大学の総長・学長が述べる式辞…
 勉強法
勉強法
以前ご相談を承った、算命学を学ばれている方から、 『算命学に興味を持ち始めた頃は、「あの人はどうしてこうなの?」「私ってどうしてこうなの?」ということの理由がどんどん納得できてスッキリしていたのですが、次第にわからないこ…
 勉強法
勉強法
算命学を勉強し始めて以来、ノートを書くことが劇的に増え、100sheetsのノートを2ヵ月に一冊くらい使っています。 それでも最近はアウトプットが増えたこともあって以前よりはかなり減っていて、最初の頃などは、1ヵ月に一冊…
 勉強法
勉強法
このところ、バタバタと家を探していて、メインブログの更新が2日ほど滞っていました。「家を探す」といって、私の家ではなく、弟家族の家。 赴任先から戻ってくるにあたり、進学する学校が決まってから家を探す、という多少無謀なこと…
 勉強法
勉強法
一つの分野をこんこんと勉強していると、知識と知識をつなぐストーリーというのが見えるようになる、聞こえるようになる、ということがあります。 書いてあること、学んだことからダイレクトに分かることではなく、それをつなぐロジック…
 勉強法
勉強法
先日、note のサークルでの zoomMTG を実施した際に、お店をされている自営業の参加者の方が、 コロナで補助金がびっくりするほど出るので、あちこちの神社へのお賽銭として万札をばら撒いておられる、というお話をされて…
最近のコメント